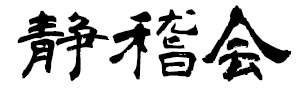稽古をしていると必ず出てくるフレーズがあります。
「力を抜きましょう」
これほど分かりにくいいことはありません。
どこをどれだけどのくらいの間、力を「抜け」ば良いのか?
特に初心者には分かりにくいと思います。
最初に断わっておきますが、これに対する具体的な回答は持ち合わせておりません^_^;
動きの大きな武術から話をするとなかなか分かりにくいので、対極にある動かない坐禅をお話したいと思います。
ここでは純粋に坐るという「運動」にのみスポットを当てて話をします。
坐禅は1回あたり30〜40分ほど坐り続けます。ただただ坐り続けるわけですが、坐り慣れない方は苦痛だと思います。そしてここでも坐禅の師は「力を抜きなさい」とおっしゃいます。
ここで武術と同じ疑問が出てくるわけです。
「力を抜けって言われても、本当に力を抜いたらグデタマ(わからない人は検索してみて下さい)みたいになっちゃうよ」と心の中で思っている方は多いのではないでしょうか?
長時間坐り続けていると分かりますが、肩や脚、腕、背筋などすべてに力を入れていると疲れてきます。当たり前ですが疲れてくると同じ姿勢でいることができなくなります。
何度も何度も長時間坐ることにトライしていくと、だんだんとわかってくるのですが、力を抜くところと「力」が必要なところがあることに気がつきます。
背中を丸める姿勢だとやがて呼吸が苦しくなります。また長い時間を坐るにはその姿勢自体も苦しくなってきます。
では胸や肘を張って腰を反らす姿勢はと言うと、これも肩や腰回りが苦しくなってきます。
一番長く坐るためには、肩や腕、脚などの胴体に付いている部分は力を抜き、頭、首、背骨、坐骨のラインを支えられる最低限の伸ばす「力」だけを残すと長く坐れます。まあこれもあくまでも私の感覚です。
一番良い形は坐り続けることで個々人が感じて掴んでいくしかありません。ポイントは短時間ではなく長く坐り続けられる姿勢ということ。坐り始めは正しく坐らなければならないとの思いから、身体からの声が聞こえてきませんので、どうしても我慢して辛くなります。大体、そこで坐禅を止めてしまいます。
個人的には武術もこれと同じだと思っています。「力を抜け」も稽古を続けていると、だんだんとわかるのかなぁと。
そういえば以前から思っていたのですが、鎌倉の大仏様はどう見ても猫背ですよね。坐禅でよく言われる「正しい坐り方」ではありません。でも他人が坐るわけではなくどこまでも自分が坐るわけですから、何より自分らしく坐ることが大切なんだと思います。